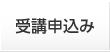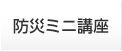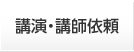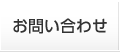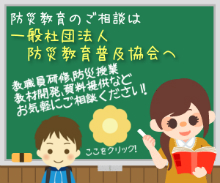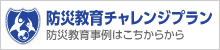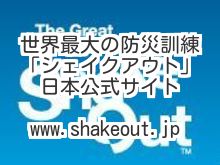2018年02月02日
※この講座は終了しました。
【神奈川第66期 相模原・県央 災害救援ボランティア講座】
募集要項は、こちらよりダウンロードできます ⇒ 神奈川第66期募集要綱ver1.0
< 日 程 > ※おおむね9:00~17:00。
3月6日(火):災害に関する基礎的知識(講義とワークショップ)
3月7日(水):災害ボランティアの基礎や日頃の活動事例、実技体験
詳しくは、募集要項をご覧ください。
< 会 場 >
神奈川県総合防災センター・管理棟3階大会議室 厚木市下津古久280
※ 車やバイクでのご来場が可能です。(事前申請制)
ご希望の場合はお申し込み時に「車種」と「ナンバー」を申請ください。
※ 小田急線「愛甲石田」駅から会場付近までバスも運行しています。(運行本数少)
< 申 込 >
定員50名。3月1日(木) または 定員に達し次第〆切。
受講料:(一般)15,000円 (学生)10,000円
お申し込みは当推進委員会事務局まで。メールフォームからのお申し込みも可能です。
カテゴリ:講座日程