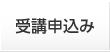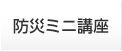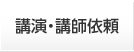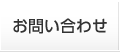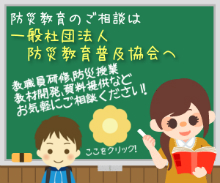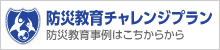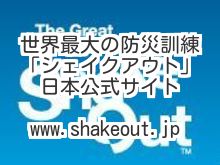平成24年(2012年)
01月08日 横浜市消防局・出初式
01月13日 SL-A福祉部会
01月17日 ShakeOut提唱会議結成
01月17日 阪神・淡路大震災祈念日
01月20日 JBU第6期基礎講座西コース(21/福岡)
01月21日 西東京市防災アクション講演会
01月22日 千葉県SLネット活動報告会
01月28日 船橋市民防災フェア 防災講演
02月03日 都立広尾高校防災教育
02月03日 東京都北区困難者対策訓練
02月07日 神奈川第53期 災害救援ボランティア講座 開催(8,13/厚木)
02月08日 都立八王子北高校防災教育(9,10/八王子)
02月08日 江東区NPO市民活動カフェ防災研修会
02月10日 SL-A福祉部会(国立障害者リハビリテーションセンター見学)
02月10日 茂原市災害対策コーディネーター講座
02月11日 2011年度防災教育CP活動報告会 運営
02月18日 茂原市本納小学校家庭教育学級
02月 やまと市民MENS講座(大和市) 講師派遣
02月19日 小平市立小平小学校防災教育
02月24日 江東区立南砂第二中学校教員研修
02月24日 さいたま市立上大久保中学級保健委員会防災教育
02月26日 福島学院大学付属幼稚園DST研究広報
02月29日 都立広尾高校防災教育
03月02日 東京第70期立教大学 災害救援ボランティア講座 開催(3,10/池袋)
03月02日 江東区立南砂第二中学校防災教育
03月03日 福島学院大学付属幼稚園DSTワークショップ
03月09日 千代田区一斉防災訓練(シェイクアウト訓練)協力
03月11日 東日本大震災祈念日
03月 千葉市災害復興イベント
03月13日 都立大江戸高校生徒防災研修
03月15日 都立大江戸高校防災一斉体験学習
03月15日 千葉第30期第2回我孫子講座(16,17)
03月17日 そなエリア東京防災キャンプ(18/有明)
04月06日 JBU第7期基礎講座西コース(7/福岡)
04月12日 第35回定期委員会
04月15日 応急部会被災地支援Voバス(~18/岩手)
04月20日 JBU第7期基礎講座東・中コース(21/東京・滋賀)
05月12日 第14期上級講座(13,19/有明)
05月20日 千代田区第31期専修大学 後期災害救援ボランティア講座 開催(26,27/神田)
05月20日 佐倉市上宿町会防災講演
05月27日 千代田区第32期上智大学 災害救援ボランティア講座 開催(6月2,3/四谷)
05月 千葉県SLネット合同研修会
06月01日 JBU第8期基礎講座中コース(2/滋賀)
06月04日 足立区男女共同参画プラザ研修
06月07日 SLネットワーク全体交流会(有明)
06月09日 千代田区第33期明治大学 災害救援ボランティア講座 開催(10,16/駿河台)
06月18日 日本私立大学連盟学生生活支援研究会総会基調講演(法政)
06月22日 JBU第8期基礎講座東コース(23/東京)
06月23日 千代田区第34期法政大学 災害救援ボランティア講座 開催(30,7月7日/市ヶ谷)
06月24日 大磯町防災講演会 講師派遣
06月27日 三菱重工労組長崎造船支部研修(28/長崎)
06月29日 防災教育支援研修会(有明)
06月30日 安全衛生フォーラム(有明)
06月 星ヶ丘地区社協福祉学習会(相模原市) 講師派遣
07月04日 関東学院大学災害ボランティア事前研修
07月09日 都立五日市高校定時制避難訓練指導
07月10日 第36回定期委員会
07月11日 千葉第31期 災害救援ボランティア講座 開催(12,13/千葉市)
07月13日 都立鎌田高校宿泊防災体験協力
07月20日 ㈱ベネッセコーポレーション防災研修
07月23日 神奈川第54期横浜 災害救援ボランティア講座 開催(24,26)
07月25日 企業防災研修会(平田直教授講演会/KKR)
07月27日 JBU第8期基礎講座西コース(28/福岡)
08月01日 東京第71期工学院大学 災害救援ボランティア講座 開催(2,3/新宿)
08月04日 江東区障害者福祉センター防災講演会
08月 茂原市茂原小学校防災研修
08月06日 東京第72期中央大学 災害救援ボランティア講座 開催(7,8/八王子)
08月 旭市教育委員会防災講演会(海上)
08月08日 千葉県教育庁防災教育実践研修会
08月10日 東京第73期一橋大学 災害救援ボランティア講座 開催(11,12/国立)
08月18日 そなエリア防災キャンプ(19/有明)
08月18日 小平市社協Vo講座(25,9/1,8,15/小平)
08月24日 防災教育支援研修会(有明)
08月26日 JBU基本教育全国版(27,28/釜石)
08月25日 NHK防災パーク協力(26/渋谷)
08月30日 茂原市立豊岡小学校防災研修
09月01日 九都県市合同防災訓練
09月02日 千葉市若葉区防災訓練
09月03日 都立練馬高校防災講演会
09月14日 東京第74期目白大学 災害救援ボランティア講座 開催(15,16/新宿)
09月16日 白井市自治会連合会防災講演会
09月20日 極地研究所見学(応急部会)
09月26日 江東区立第二南砂中学校教員研修
09月27日 船橋市男女共同参画センター防災講座
09月28日 千葉第32期第2回船橋 災害救援ボランティア講座 開催(29,30/船橋)
09月 都立清瀬高校防災宿泊体験講習
09月30日 豊島区立椎名町小防災体験学習
10月07日 千代田区第35期専修大学 後期災害救援ボランティア講座 開催(13,14/神田)
10月10日 県民大学講座(茨城県行方市) 講師派遣
10月12日 足立区ボランティア連絡会災害研修
10月13日 2012年度防災教育CP防災教育交流フォーラム 運営(14)
10月16日 八王子市男女共同参画センター防災講座
10月13日 千代田区第36期明治大学 後期災害救援ボランティア講座 開催(27,28/駿河台)
10月16日 八王子市男女共同参画防災研修
10月16日 米国ShakeOut視察(-20/カリフォルニア)
10月21日 座間ハイツ 防災・減災体験フェアー 指導
10月30日 千葉県災害ボランティアセンター中核スタッフ養成研修(31)
10月31日 都立板橋高校防災体験事前学習
11月02日 春日部市立牛島小学校防災学習
11月08日 新座市中央公民館防災講座
11月10日 東京第75期日本大学 災害救援ボランティア講座 開催(17,18/経済学部)
11月10日 千葉第33期第3回我孫子 災害救援ボランティア講座 開催(17,24/中央学院大)
11月14日 都立練馬高校防災体験学習(15/練馬区)
11月16日 千葉県災害対策コーディネーター講座(17,18/山武市)
11月17日 上智大学防災講演会(四谷)
11月 千葉銀行清風会SL復習訓練
11月25日 法政大学チーム・オレンジ講座 講師派遣
11月28日 狭山市立入間中学校ふれあい講演会
12月01日 東京都教育支援コーディネーターフォーラム出展
12月11日 都立五日市高校定時制避難訓練
12月13日 都立板橋高校防災体験学習